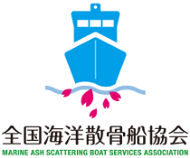海洋散骨できる場所

海洋散骨ができる場所とは?神奈川の海や東京湾で散骨はできる?
海洋散骨をする場所は、周りに配慮して選ぶ必要があります。
ここでは、一般的なルールや自治体の条例、ハワイなど海外での取り決め、神奈川の海で散骨する方法や、海洋散骨に関する場所以外の基本的なルールについて解説します。
海洋散骨、場所選びのルールとは?
海洋散骨は法律での決まりはないものの、散骨できる場所とできない場所があります。
できる・できないを決めているのは、2つの規定です。
1つは一般社団法人日本海洋散骨協会が定める義務規定です。
この協会では、散骨場所の選定基準と散骨を行う際のルールが定められています。
2つ目は、自治体ごとの条例です。
自治体によっては、散骨に関する決まりが条例で定められています。
まずは1つ目の一般社団法人日本海洋散骨協会が定める規定を見てみましょう。
一般社団法人日本海洋散骨協会は、加盟業者に対し、散骨場所の選定義務を以下のように定めています。
“1.加盟事業者は、人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。
【注2】【注3】
【注2】一般市民の目に触れる場所で散骨を行うことを避けるとともに、遺骨が風に吹かれて一般市民にかかるなどしてトラブルが発生することを防止するため、散骨に立ち会う者以外がいない場所で行う必要があります。
【注3】河川や湖沼は、水源になっている可能性があります。水源に散骨を行った場合、その水を飲む方々の心情を害するおそれがあるため、水源での散骨は禁止する必要があります。
2.加盟事業者は、散骨のために出航した船舶においてのみ散骨を行い、フェリー・遊覧船・交通船など一般の船客がいる船舶や漁船において散骨を行ってはいけません。
3.加盟事業者が海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避け、一般の船客から視認されないように努めなければいけません。“
(一般社団法人日本海洋散骨協会「海洋散骨ガイドライン」より引用)
要約すると、
・陸から2キロほど離れた、人目につかない場所を選ぶ
・水源になるような河川や湖沼は避ける
・漁場や航路は避ける
・散骨のためのクルーザーからのみ散骨できる
ということです。
このルールに則り自分で海洋散骨をするとなると、漁場や航路を調べ、クルーザーを手配して陸から離れた場所で散骨しなければなりません。
トラブルを避けるために、専門の海洋散骨業者に依頼するのが安心です。
散骨できない地域とは?自治体ごとに条例が定められている
散骨自体が禁止されている地域もあります。
日本国内で、散骨に対する条例が設けられている地域は以下の通りです。
海洋散骨で人気の東京や沖縄には、条例はありません。
【散骨が事実上禁止されている地域】
・北海道長沼町
・宮城県松島町
・埼玉県秩父市
【散骨にあたり届出が必要な地域】
・北海道岩見沢市
・北海道七飯町
・埼玉県本庄市
・神奈川県湯河原市
・静岡県御殿場市
・静岡県熱海市
・静岡県伊東市
・静岡県三島市
・長野県諏訪市
これらの地域では、散骨に関する条例が定められています。(2021年3月現在)
事業者に対する条例であり、個人に関しては言及していないところもあるものの、トラブル防止のためにも個人で散骨する場合にも確認した方がよいでしょう。
各自治体の条例を以下に記載いたしますので、気になる自治体がある方はご確認下さい。
【北海道】
●長沼町
第11条 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。
●岩見沢市
第7条 散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない。ただし、次条の規定による届出をした者がその届出に係る区域において散骨を行う場合は、この限りでない。(散骨場以外の区域における散骨の届出)
第8条 散骨場以外の区域において散骨を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。(報告の徴収及び立入調査等)
●七飯町
第1条 七飯町内において事業者による法定外の葬法が提起された場合には、地域における行政を自主的かつ町民の意思尊重の下に実施するため、本要綱を制定する。
第3条 町長は、事業者が法定外の葬法に関する事業を計画する場所を設定するときは、次に掲げる区域等を除くよう指導し、事業者はこれを遵守するものとする。
・次の施設にかかる土地の敷地境界から110メートル以内の区域
・学校教育法、社会教育法、医療法、介護保険法、身体障害者福祉法、児童福祉法、
知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、老人福祉法
に基づいて設置された施設
・都市公園法第2条第1項に規定する都市公園
・都市計画法第33条第1項第2号の規定により設置された公園、広場その他の公共の用に
供する空地
・その他、国道、道々等交通の頻繁な道路、軌道、河川、公共施設・公共的施設及び人家
・都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域内の旧住宅地造成事業に関する法律
により造成された団地の区域内、50戸連たん地域内、その他町長が集落をなしていると認める区域内及びその境界から110メートル以内の区域
・都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域内及びその境界から110メートル以内の区域
・都市計画道路函館新道及び七飯通の都市計画決定区域及びその境界から200メートル以内の区域
・水道水源等に影響を及ぼすおそれのある区域(取水区域及び取水区域の境界から500メートル以内の区域)
・自然公園法に規定する自然公園の区域
・北海道自然保護条例第6条第2項の規定に基づき指定された地区
・七飯町と隣接する他の市町との区域境から500メートル以内の区域
・その他、町長が公衆衛生その他公共の福祉に著しい影響を与えると認める場所
七飯町の葬法に関する要綱 より
【宮城県】
●松島町
第8条 何人も、みだりに焼骨を散布してはならない。
【埼玉県】
●本庄市
第4条 散骨場を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
●秩父市
第7章 焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止(第36条−第42条)
秩父市環境保全条例 より
【神奈川県】
●湯河原町
第6条 散骨事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町の許可を受けなければならない。
【静岡県】
●御殿場市
第3条 散骨場を経営しようとするものは、許可申請を行う前に、規則で定めるところにより関係人に対し、当該散骨事業の計画について、説明及び協議するための説明会を開催しなければならない。
第4条 計画者は、許可申請を行う前に、あらかじめ、当該散骨場と境界を接する土地所有者の同意を得なければならない。
第5条 計画者は、許可申請を行う前に、当該散骨事業の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第6条 計画者は、散骨事業を行おうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
●熱海市
第3条 散骨場を経営しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
●伊東市
第3条 散骨場等を経営しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
●三島市
第5条 散骨場の経営等をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
【長野県】
●諏訪市
第3条 散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第9条 墓地又は散骨場の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1)国県道その他重要な道路、鉄道、軌道及び河川から50メートル以上隔てること。
(2)人家等ふくそう地より200メートル以上の距離を有すること。
(3)土地は高燥な所を選び湿潤な所を避けること。
(4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
(5)境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。 (墓地又は散骨場の施設基準)
神奈川の海や東京湾でも海洋散骨はできる
首都圏にお住いの方に人気の海洋散骨エリアの1つが神奈川の海です。
神奈川県内では湯河原に条例があるものの、その他のエリアに具体的な取り決めはありません。
人気の湘南や葉山沖のエリアでも、海洋散骨が可能です。
海洋散骨のクルーザーに乗船する場合には、自分で出航する港まで足を運ばなければなりませんが、東京湾や神奈川の海であれば首都圏から行きやすいものです。
COMPASSでは葉山沖を中心に、江の島沖、鎌倉沖、三浦沖、茅ケ崎沖、羽田沖での散骨が可能です。
自社クルーザーにて、ご遺族の心に寄り添う海洋散骨をお手伝いしております。
海外での海洋散骨、ハワイでもできる?
海洋散骨は、海外で行うこともできます。
ただし国内と同様、海外でも海洋散骨の関するルールが設けられています。
日本同様、散骨したい国の法律や地域の条例などを確認しなければなりません。
さらに散骨をする現地の宗教事情にも配慮すべきです。
散骨がよく行われている地域かどうか、宗教上散骨がどのようにとらえられているかなど、事前に調べておくと、不要なトラブルを回避できるでしょう。
<ハワイで散骨するには?>
ハワイでも海洋散骨は可能です。
ただし州の法律で「海岸から3マイル以上離れた沖合」と決められています。
そのため、クルーザーのチャーターが必須です。
海外で海洋散骨する場合には、日本で遺骨を粉骨し飛行機の手荷物として持参します。
国内同様、やり方次第で費用は異なります。
ただし渡航費や宿泊代が必要ですので、国内で海洋散骨をするよりもかかる費用は高額でしょう。
知っておきたい散骨のルール 場所以外の3つの注意点
海洋散骨を行う際には、場所以外にも注意すべき3つのポイントがあります。
【散骨のルール】
・遺骨は適切に粉骨する
・自然に還らない副葬品は海に撒かない
・親族の理解を得て行う
●遺骨は適切に粉骨する
海洋散骨するには、前もって遺骨を一片が約2mm以下の粉末状に粉骨しなければならないというルールがあります。
目で見て骨だとわかる状態の遺骨の散骨は、法律違反です。
●自然に還らない副葬品は海に撒かない
海洋散骨の際には、環境面にも配慮が必要です。
故人の大切にしていたものや身に着けていたものと一緒に送り出したいという思いもあるでしょう。
またお花を添えたり、お酒を添えたりするのもよくあることです。
しかし自然に還らないものを海に流してしまうと、環境汚染に繋がるだけでなく、どこに漂着するかわからずトラブルのもとです。
自然に還らないものは撒かない、量は少しにするなど配慮が必要です。
●親族の理解を得て行う
海洋散骨は近年注目されている葬送ではあるものの、まだまだ一般的とは言えません。
海洋散骨を検討する際には、事前に親族の理解が必要です。
海洋散骨がどういった供養方法なのか、なぜやりたいのかなど、よく話し合っておきましょう。
海洋散骨は法律的に違法ではないものの、注意すべき点が多いものです。
海洋散骨する場所だけとっても、周囲への配慮が欠かせず、クルーザーをチャーターしなければなりません。
海洋散骨をする際には、専門的な知識を持つ業者に依頼する方が、安心して故人を送り出せるでしょう。
海洋散骨専門「COMPASS」の特徴
COMPASSは「ご遺族の心に寄り添う」ご供養を最も大切にしています。
散骨にあたり、故人様を大切に想い丁寧に扱うことは当たり前のこと。
その上で、「これからを生きていくご遺族のみなさまがしっかりとご自身のお気持ちに向き合い、新たな1歩を踏み出せるようサポートしたい」というのが私たちの強い願いです。
散骨にあたっては事前に打ち合わせを行い、ご遺族の方がしっかりと悲しみに向き合い感謝を表現できるようお手伝いしております。ご遺族のみなさまのお気持ちやご要望を、ぜひお聞かせください。
またCOMPASSでは、手元供養のサービスもご用意しております。
お骨の一部をお手元に残すことで、ご遺族のみなさまのこれからの新たな1歩をお支えするためのものです。
散骨や手元供養をご検討の際には、「ご遺族の心に寄り添う」COMPASSに、ご相談くださいませ。